「103?106?130?数字がたくさん出てきて何が違うの?」
結論、税の“扶養・控除の壁”と社会保険の“被扶養・加入の壁”が別物だから混乱します。
本記事はこの2系統を同じ土俵で整理し、“今年はどこに着地するのが最適か”を最短で判断できるように作りました。
このページだけで、要点→判定→最適ルート→ToDoまで完結します。
✅ 2025年(令和7年)対応
①給与所得控除の最低保障が55万→65万円に引上げ【⇒税の“103万の壁”の目安は概ね「123万円」へ変わります】。
②あわせて基礎控除も引上げ(段階的)されました。国税庁
・配偶者特別控除の満額レンジが「150万以下→160万以下」に拡大(世帯の所得制限など従来要件は存置)。配偶者控除と配偶者特別控除の違い
③社会保険は、106万円の壁(週20h・所定内賃金等)の要件見直しが法律で決定。賃金要件の撤廃は公布から3年以内に実施予定、企業規模要件は今後10年かけ縮小・撤廃のロードマップ。現時点の適用状況は本文で解説。厚生労働省
④130万円の壁(被扶養判定)は「月額換算・継続性」で判断。一時的な超過は「事業主の証明」で猶予、ただし3年連続超過で扶養外の運用あり。厚生労働省
⑤19~23歳(配偶者除く)の被扶養要件は130万→150万円に緩和(2025/10/1以降の認定)。
他の記事
1. まずは全体像(税/社保の違い)
- 税の壁(所得税・住民税):配偶者控除/配偶者特別控除を受けられるかどうかという壁。主に年収123万(旧103万)/160万(旧150万)/201万が壁となる。年収ベースで判断。
- 社会保険の壁①:配偶者の被扶養に入れるかどうかという壁。およそ年収130万が壁となる。年収の見込みで見られるためその月収が続くと130万円を超えるかどうか月収ベースで判断。
- 社会保険の壁②:「週20h以上」「月の所定内賃金8.8万円以上」「2か月超見込み」「学生でない」「従業員数51人以上」を満たすと自分が社保加入(自動的に被扶養から外れる)
2025年対応「超短縮」早見表
| 壁 | 区分 | 何が変わる/起きる | 判定の軸 | 2025のポイント |
|---|---|---|---|---|
| 123万円 (旧103万円) | 税 | 所得税・住民税(配偶者控除の前提)のライン目安 | 年収ベース | 給与所得控除65万+基礎控除58万の組合せで概ね123万に。基礎控除は合計所得に応じ段階加算あり。国税庁 |
| 106万円 | 社保② | 本人が社会保険加入(被扶養から外れる) | 週20h・所定内賃金・2か月超・学生除外・企業規模等 | 賃金要件撤廃(3年以内目標)・企業規模要件の段階撤廃が法律で決定。現時点の就労先要件は必ず最新を確認。厚生労働省 |
| 130万円 | 社保① | 配偶者の被扶養「可/不可」 | 月額換算(約108,334円が“続く”か) | 通勤手当は年収に含めて判定。一時的超過は事業主証明で救済、3年連続超過で解除。JTB健康保険組合 |
| 160万円 (旧150万円) | 税 | 配偶者特別控除の満額レンジ | 年収ベース | 満額の上限が160万へ。超えると緩やかに減額、201万円超でゼロ。 |
| 201万円 | 税 | 配偶者特別控除が対象外に | 年収ベース | 従来どおりの上限を維持。 |
2. 各“壁”の要点と判定
2.1 123万円(旧103万円)の壁(所得税の基礎ライン)
- 影響:所得税・住民税
- ざっくり:給与所得控除後の課税が出ないレンジの目安。
- ポイント:配偶者控除の前提に絡む/住民税の非課税ラインは自治体差あり。
2.2 106万円の壁(社保の加入義務・特定要件)
- 影響:社会保険
- ざっくり:一定規模の企業+週の所定労働時間等の要件+年収見込みが106万以上でご本人が社保加入(被扶養から外れる)。
- 2025年法改正で、①賃金要件の撤廃(公布から3年以内)、②企業規模要件の段階撤廃(10年スパン)が決定。移行中は就労先の最新適用を必ず確認。厚生労働省
- ポイント:企業規模・雇用期間見込み・学生除外などで複合的に判定される。
2.3 130万円の壁(被扶養の認定・月ベース)
- 影響:社会保険
- ざっくり:社会保険の被扶養に入れるかの代表ライン。“月額換算”や臨時収入の扱いが論点。
- 19~23歳(配偶者除く)は150万未満へ緩和(2025/10/1以降の認定)。家族(子等)の扶養実務はこの新基準に注意。
- ポイント:たまたま一時的に超えたケースでは被扶養から外れないことも(継続性の判断)
2.4 160万(旧150万)・201万円(配偶者特別控除レンジ)
- 影響:所得税・住民税
- ざっくり:160万を超えてもいきなり配偶者特別控除はゼロにならず、緩やかに控除が減る。201万超で配偶者特別控除がなくなる。
- ポイント:「超えるならどこまで」の設計が有効(がっつり稼ぐ/副業配分など)。
早見表(テンプレ)
| 壁 | 分類 | 主な影響 | 判定の軸 | 要点 |
|---|---|---|---|---|
| 103万 | 税 | 配偶者控除の前提 | 年収合計 | 年末調整でギリ調整が定番 |
| 106万 | 社保 | 本人の社保加入義務(要件あり) | 年収見込み+就労要件 | 企業規模・週時間・雇用期間など複合 |
| 130万 | 社保 | 被扶養 可能/不可 | 月額換算(継続性) | 一時的超過の扱いに注意 |
| 150万 | 税 | 配偶者特別控除の減額開始 | 年収合計 | 緩やかに減るので設計余地あり |
| 201万 | 税 | 配偶者特別控除の対象外 | 年収合計 | 超えるなら稼ぎ切る戦略へ |
3. ありがち誤解と落とし穴
- ボーナス:税・社保で取扱いが異なる。月換算と継続性を必ず確認。
- 交通費・通勤手当:非課税枠と年収カウントで混乱しやすい。
- 副業収入:事業/雑所得の所得計算が混ざると判定がズレる。
- 年内/年またぎ:標準報酬の見直し時期・住民税の決定タイミングをまたぐと体感差が出る。
🔎 詳細は各クラスター記事へ内部リンク
・配偶者控除と特別控除の違い
・103/106/130の壁を解説
4. ケース別の最適解
4.1 パート(配偶者が会社員)
- 超えない最適化:シフト調整、交通費、賞与の有無、ふるさと納税上限の目安確認
- あえて超える:106超なら社会保険の保障性と年金を評価。勤務先の規模・所定労働時間で要件チェック
4.2 Wワーカー(副業あり)
- 税区分(給与/事業/雑)と経費を正しく整理
- 年末の損益通算や配偶者特別控除レンジの最適化
4.3 学生・シニア
- 学生の106除外、シニアの在職の扱いなど“例外ルール”を確認
4.4 産後・育休期
- 出産手当金・育休給付と就労収入の関係
- 年またぎの標準報酬・税額への影響
5. 今年の調整ToDo(年末~確定申告)
- 年末調整前:概算表で今の着地を確認(時給×週時間×月)
- ギリ超え対策:年内シフト/賞与調整の可否を事前に相談
- 申告期:副業の区分・控除の最適化、医療費・寄付金(ふるさと納税)の整理
- 6~10月:住民税決定通知・標準報酬見直し→再設計
6. よくある質問(FAQ)
Q1. 123万(旧103万)・106万・130万の違いがまだピンときません…
A. ざっくりこう分けると整理しやすいです。
- 123万円(旧103万円)160万円(旧150万円)=税金(所得税・配偶者控除・配偶者特別控除)側の目安
- 106万円=会社で本人が社会保険に入るかを見るライン(週20h・月8.8万円・2か月超・学生以外・規模要件などセット)
- 130万円=配偶者の被扶養にいられるかを健康保険で見るライン(多くは月108,334円目安)
つまり、税と社保で“見ているもの”が違うので、「123万はOKだけど社保ではNG」みたいなことが起こります。
Q2. ボーナスや一時的な残業で130万円をちょっと超えたらすぐ扶養から外れますか?
A. 多くの健保は「継続的かどうか」を見ます。ボーナス1回で一時的に超えただけならセーフになることもあるので、まずは加入している健康保険(協会けんぽ・組合健保など)に確認してください。逆に、毎月その水準が続く見込みだと扶養外の判断になりやすいです。
Q3. バイトやパートを2つしている場合は、収入は合算されますか?
A. はい、合算して判定されることがあります。特に社会保険のほうは「複数事業所で働いているか」「全部でどのくらいの収入か」を見ることがあるので、片方だけで130万円未満でも、合計すると外れるケースがあります。勤務先にも必ず伝えておきましょう。
Q4. 通勤手当(交通費)はこの“壁”の年収に含めて考えたほうがいいですか?
A. 税金では非課税通勤手当を年収に含めないのが普通ですが、社保(被扶養の判定や標準報酬)では通勤手当も含めて月額を見る運用が多いです。安全にいくなら「交通費も含めた金額」で130万円・106万円を見ておくとズレが起きにくいです。
Q5. どれを優先して守ればいいかわからないのですが…
A. 基本はこの順で考えると決めやすいです。
- まず「今は世帯で保険料を増やしたくない」なら130万円(被扶養)を優先
- 会社が106万円の適用対象で、あなたも条件を満たすなら106万円の加入のほうが先に来ると想定
- そのうえで「税面でどれくらい控除が残るか(123万/160万/201万)」を調整
最終判断は会社の就業規則・健保の基準に従ってください。
Q6. 今後(2025年以降)また金額が変わることはありますか?
A. 税・社保のラインは物価・制度改正・適用拡大でちょこちょこ動くことがあるため、年1回は公式(国税庁・厚労省・加入健保)をチェックしてください。「扶養の壁ナビ」側でも分かる範囲でアップデートしていきます。
8. 一次情報の参照先
- 国税庁:「配偶者特別控除(タックスアンサー No.1195)」
- 国税庁:「配偶者控除・配偶者特別控除の見直し」
9. 更新履歴
最終更新:2025-10-12
- 初版公開/早見表・診断セクション追加
他の記事
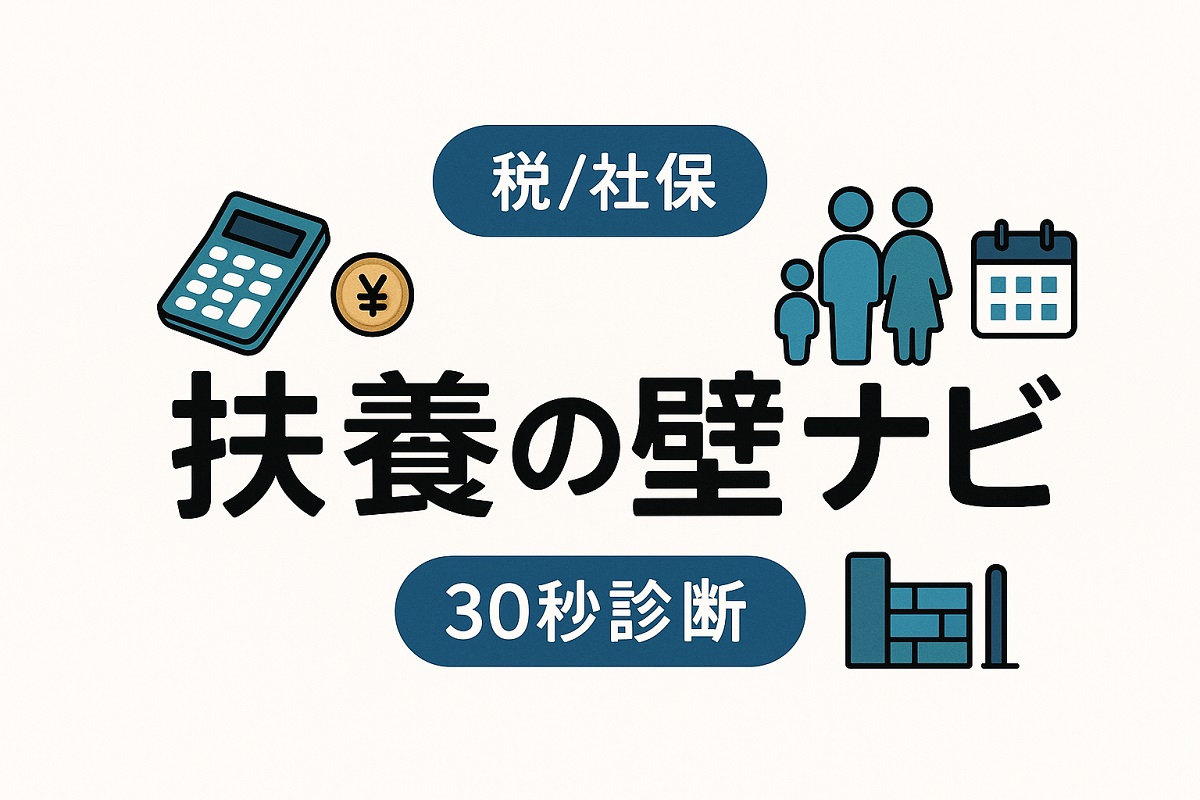




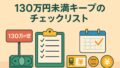
コメント