PR:本記事にはアフィリエイト広告が含まれます。リンク先での購入等により、当サイトに報酬が発生する場合があります。
税理士試験とは?
税理士試験は、会計・税務のスペシャリストとしての知識を問う国家試験です。
毎年8月に実施され、受験者数は約3万人。合格までに複数年かかるのが一般的です。
試験制度の概要
受験資格
税理士試験には受験資格があります。
主なものは以下のとおりです。
- 会計学の科目合格者(簿記1級合格など)
- 大学で法律学または経済学を一定単位以上修得
- 日商簿記1級・全経上級合格者
- 税理士試験科目合格者(科目合格を重ねて資格取得を目指す方法)
👉 社会人の場合、日商簿記1級を経由して受験資格を得るのが現実的なルートです。
試験科目と合格条件
税理士試験は 全11科目 から構成されます。
- 必須科目(2科目)
- 簿記論
- 財務諸表論
- 選択必須(1科目)
- 法人税法
- 所得税法
- 選択科目(2科目)
- 相続税法
- 消費税法
- 酒税法
- 固定資産税
- 住民税
- 事業税
- 国税徴収法
合格には 合計5科目の合格 が必要です。
1年で5科目受験することも可能ですが、一般的には2〜3年かけて分割受験するのが主流です。
科目選び戦略
税理士試験はどの科目を選ぶかで合格までの道のりが変わると言われています。
ここでは、私自身の経験や受験生の傾向をもとにした戦略をまとめます。
1. 必須科目(簿記論・財務諸表論)は最優先
- 試験の基礎となるため、まずはこの2科目を早めに合格することが重要です。
- 簿記や会計の土台を固めることで、他の税法科目の理解もスムーズになります。
2. 選択必須(法人税法 or 所得税法)の選び方
- 法人税法:ボリュームが多く難易度が高いが、受験者数も多く王道。将来的な実務でも役立つ。
- 所得税法:範囲は広いが法人税よりはボリュームが少ない。独立開業を視野に入れる人に人気。
👉 一般的には「法人税法」を選択する人が多数派です。
3. 選択科目(2科目)の選び方
- 消費税法:範囲が比較的コンパクトで、実務でも必須 → 最も人気
- 相続税法:事例問題が中心。実務ニーズが高く、独立開業を考える人におすすめ
- 固定資産税・住民税・事業税:地方税科目で比較的マイナー。選択者は少ないが合格率が安定している傾向あり
- 国税徴収法:理論中心。計算量が少なく、暗記力勝負になる
👉 私は 「簿記論・財表・法人税法・消費税法・固定資産税」 で合格しました。
私の体験から感じた戦略
私は学生時代に簿記・財表を早期合格し、その後に税法科目を取りました。
- 大原やTACで体系的に学んだことで、短期間で合格できた科目もありました。
- ただし、法人税法はボリュームが膨大で独学はほぼ不可能に感じました。
- 最近はスタディングを利用し、スマホでスキマ時間に税法を学べる便利さを実感しました。
👉 「お金で合格までの時間を買うか、時間をかけて節約するか」。
どちらを選ぶかで勉強スタイルが大きく変わります。
まとめ|科目戦略で合格への道筋が変わる
- 必須科目は早めに攻略
- 法人税法か所得税法かはキャリアの方向性で決める
- 消費税法・相続税法は人気かつ実務で役立つ
- マイナー科目は戦略的に選ぶと短期合格に有利
👉 税理士試験は長期戦ですが、自分の学習スタイルに合ったスクール選びと戦略的な科目選択で大きく合格に近づけます。
まずは資料請求や無料体験からスタートし、自分に合った学習法を見つけましょう。
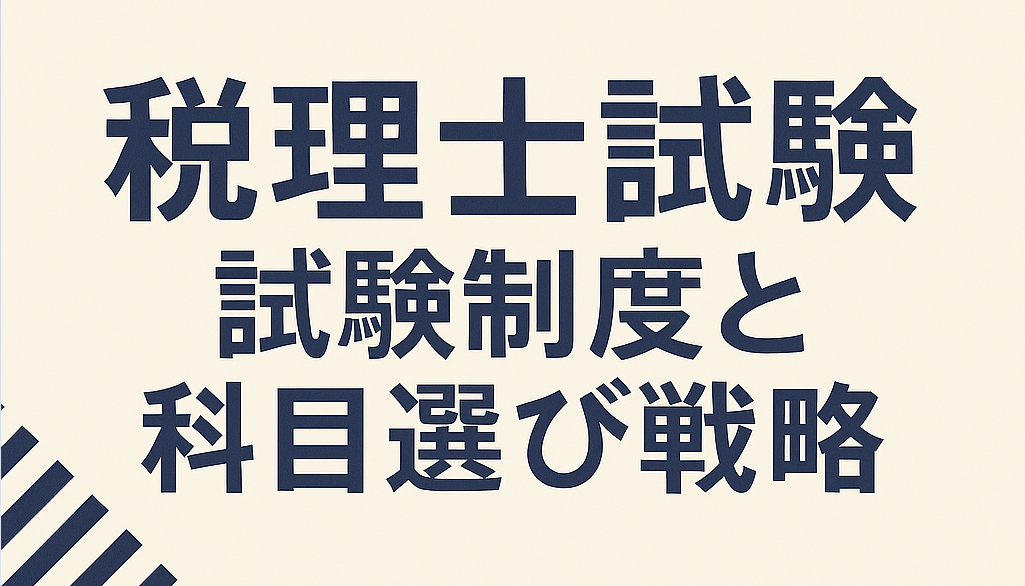


コメント