簿記は就職やキャリアアップに役立つ人気資格ですが、「3級と2級のどちらを受けるべきか」で迷う方は多いと思います。
この記事では、実際に学習した経験に加え、私の職場の部員の実例も交えながら 簿記3級と2級の違い をわかりやすく比較します。
簿記3級の特徴
- 対象:商業簿記の基礎
- 内容:仕訳・伝票・試算表・精算表・財務諸表作成など
- 難易度:入門レベル。独学でも3〜4か月で合格可能
- 勉強時間の目安:100時間程度
- 合格率:40〜50%前後
👉 初めて簿記を学ぶ人におすすめ。
会計の基本が理解でき、日常業務での仕訳や帳簿付けができるようになります。
簿記2級の特徴
- 対象:商業簿記に加えて工業簿記(原価計算)
- 内容:本支店会計・連結会計・固定資産の会計処理・標準原価計算・CVP分析など
- 難易度:中級レベル。3級の内容を理解していることが前提
- 勉強時間の目安:200〜300時間
- 合格率:15〜30%前後
👉 企業の経理や財務職を目指す方、税理士試験の基礎固めをしたい方に必須。
実例:職場の部員の成長ストーリー
私の会社に入社した部員の一人は、経理だけでなく総務や情シスも含めて「薄く広く」経験してきた状態でした。
その部員は入社後に簿記を学び始め、
- 3級を約3か月で合格
- 続いて2級を約6か月で合格
というスピードでステップアップしました。
特に印象的だったのは、3級から2級の勉強を始めて3か月くらいたったころから、実務でも一気に仕事のコツをつかみ始めたことです。
「簿記を勉強することで業務理解が深まり、仕事が楽しくなってきた」と話していました。
👉 この実例からもわかるように、簿記2級の学習は単なる資格取得だけでなく、実務の成長に直結する効果 があると感じています。
難易度の違い
- 3級:仕訳を理解すればスムーズに進められる。数学力は不要。
- 2級:範囲が広く、商業簿記と工業簿記の両方を理解する必要あり。
👉 感覚的には「3級の3倍の勉強負担」があるイメージです。
就職・キャリアでの評価の違い
- 3級
- 一般事務・経理補助でプラス評価
- 学生や就活前の資格としては有効
- 2級
- 経理・財務・会計事務所で即戦力として評価される
- 「履歴書に書いてアピールできる最低ライン」の資格
👉 事務系職種を志望するなら2級が強く推奨されます。
どちらから受けるべき?
- 簿記未経験 → 3級から
→ 基礎があると2級が格段に学びやすい - 大学や仕事で会計の基礎がある → いきなり2級も可
→ ただし独学ではハードルが高め
勉強方法の違い
- 3級:市販テキスト+問題集で十分
- 2級:テキストだけでなく、過去問演習・模試で仕上げが必須
👉 2級は範囲が広いため、独学よりも通信講座を利用する人も増えています。
もし独学で進める場合は、テキスト選びがとても重要です。
おすすめの教材はこちらの記事で詳しくまとめています。
👉 簿記3級おすすめテキスト【2025年版】
👉 簿記2級おすすめテキスト【2025年版】
まとめ|3級は入門、2級は実務レベル
- 3級:会計の基本を理解できる入門資格
- 2級:経理実務や税理士試験につながる本格資格
私の職場の部員もそうでしたが、簿記を学ぶことで 「試験合格」+「実務の成長」 の両方を得ることができます。
✅ スキマ時間で効率的に学習したい方へ
私は大原・TAC・スタディングのすべてを体験しましたが、社会人や子育て中で時間が限られる方にはスタディングが最もおすすめです。
通勤電車で仕訳問題を解いたり、夜の30分で講義を倍速視聴したり、スキマ時間を最大限活用できます。
👉 まずは無料体験で自分に合うかチェックしてみてください。
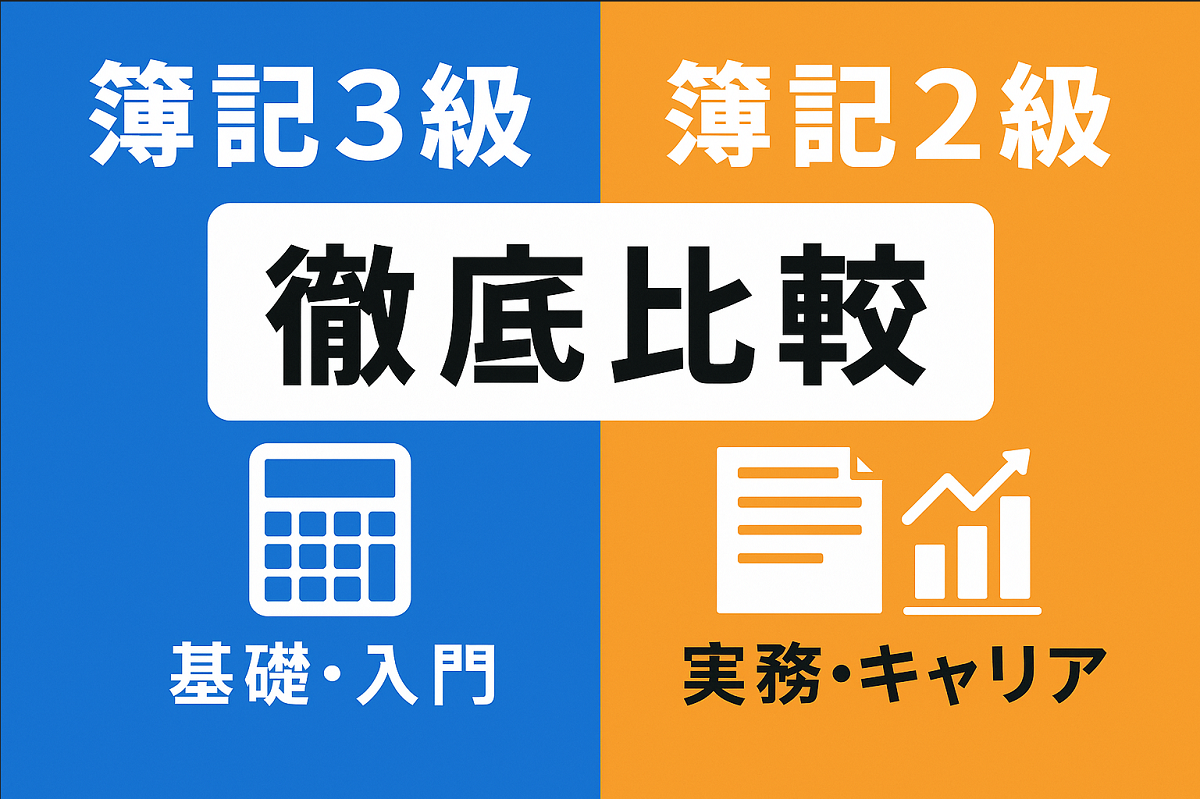


コメント